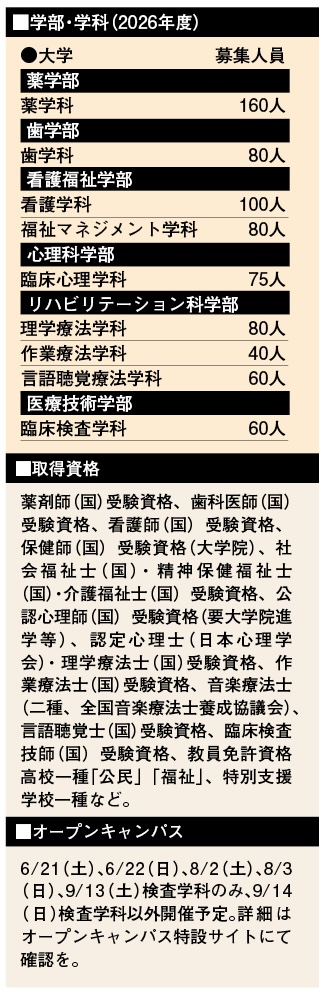北海道医療大学

(みくに・くみ)千葉大学看護学部看護学科卒業。北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻修士課程修了。北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻博士課程修了。1993 年本学就任後、看護福祉学部教授、看護学科長、看護福祉学部長、大学院看護福祉学研究科長を歴任。2024年4月から現職。
移転に向けて着々と準備。多職種連携もさらに強化
――学長就任から1年が経過しました。
三国 就任してまず行ったのが各学部長や学科長などへのヒアリングです。それぞれの現状はもちろん、強みや課題などを聞きました。本学を活性化するには、それらを横断的に共有することが大事だと考え、昨年の後半から情報交換の場を設けて意見交換を行っています。カリキュラムをはじめ、教育のあり方などについて情報共有と交換を行い、それを次に生かす段階に入っています。
――2年目は。
三国 次のステージへ向かいます。昨年、本学は7年に1度の大学基準協会による評価を受け、課題も見えてきました。内部質保証を適切に行うことが重要ですので、今年度から改善に向けてしっかりと取り組んでいきたいと考えています。
――カリキュラムなどに変更はありますか。
三国 カリキュラムではありませんが、今年度からリハビリテーション科学部で実験的な取り組みとして、「クォーター制」を導入しました。前期と後期に分けるのではなく、1年を1期から4期に4分割して授業を構築するものです。大きなメリットと考えているのは試験期間の分散です。学生の負担が減り、詰め込み型から解放されるのではと思っています。普段の授業に取り組む姿勢に変化が現れることにも期待しています。検証の結果を全学的に共有していきたいと考えています。
――独自性のある取り組みとして、高大連携協定を締結したと伺いました。
三国 近年では2022年に北海高等学校、昨年は遺愛女子中学校・高等学校に続けて、本年4月に札幌光星中学校・高等学校との高大連携協定を締結しました。同校の卒業生は医療・保健・福祉を中心に幅広い分野で活躍されています。
今回の連携により、教育活動の支援や共同研究、施設の共同利用など、相互の強みを生かして関係を強化していきたいと考えています。大学入学後に、単位認定できる仕組みとして先取り履修というプログラムの構築にも取り組む予定です。
――どのようなメリットがあるのでしょうか。
三国 医療・保健・福祉分野の人材は札幌への偏重傾向があり、地域格差が深刻化しています。対処するには、医療・保健・福祉分野に興味を持つ人材を若い世代から育成する必要があります。高大連携が、道内の保健・福祉・医療業界への貢献につながるように取り組んでいきたいと考えています。
――移転が控えている北広島市地区での連携協定も進んでいると聞いています。
三国 本学は28年春に北海道ボールパークFビレッジに移転する予定で、連携協定も移転準備の一つとして進めています。北広島市とは昨年6月、星槎道都大学とは12月に包括連携協定を締結しました。また、2つの社会福祉法人とも包括連携協定を締結しました。複数の学科の学生が実習やボランティアなどで学ばせてもらうこともあるかと思います。
――来年度以降のビジョンについて教えてください。
三国 注力分野の1つにも掲げていますが、より強力なDX人材の育成が必要だと感じています。人材不足をカバーすることができますし、高齢化社会にも対応できます。優秀な人材を数多く育成し、今後は保健・医療・福祉のDX化にも貢献できる人材を輩出していきたいと考えています。
――貴学に関わる分野は、人材不足が喫緊の課題にもなっています。どのようなことが求められているでしょうか。
三国 学生と業界をつなぐ役割を果たしていると、やはり「知識が多い人材がほしい」という時代はもう終わっていると感じます。知識はもちろん、それを適切に判断して使って、社会課題の解決につなげる。そのためには判断力、実行力、コミュニケーション能力が欠かせません。
そうした人材を育成するには、学生自ら主体的に学んでいく学修環境を整えることが必須となります。現在も取り組んでいますが、インターンシップなどをさらに充実させていきたいですね。
また本学に限ると、医療系総合大学の強みを生かすことが今後も重要です。強調したいのは、本学ならではの特色である多職種連携教育です。保健・医療・福祉分野は切れ目のない連携が大切になっていますので、学生時代からさまざまな職種と連携できるようなカリキュラムを構成しています。
今後、北広島市へ移転してキャンパスが一つになることで、他学部の学生同士がさらに連携・交流しやすくなります。現在ワーキンググループを立ち上げ、本学における多職種連携教育をさらに強化する準備を進めているところです。